小澤征爾が1968年に32歳にしてシカゴ響を振ったストラヴィンスキーの『春の祭典』。村上春樹との対談の中で、小澤は「これは(レコード会社の選曲ではなく)僕がやりたくてやったもの」と語っている。そこで語られている裏話が面白い。
その『春の祭典』の吹き込みにはね、裏話があるんです。実はね、結局幻になっちゃったんだけど、ストラヴィンスキーがその直前に『春の祭典』を書き換えたんですよ。改訂版っていって、小節線を変えちゃったわけです。もう本当に信じられない。僕らが勉強したものとはがらっと違うものに書き換えられてしまった。これはね、指揮者とか演奏家にとってはもうまさに青天の霹靂です。こんなのはとてもできない、と僕なんかは思ったわけです(中略)それでストラヴィンスキーは、ぼくにそのレコーディングをしてくれっていうわけです。で、録音しました。(中略)シカゴ・シンフォニーと、旧版と改訂版、そのときは両方を録音しています
『小澤征爾さんと音楽について話をする』(新潮文庫、2014), pp. 185-187
両方を録音したものの、改訂版は「これは駄目だ」と小澤もオーケストラも思ったという簡素化されたバージョンで、結局発売されなかったという。お蔵入りになったということだが、お蔵に入っているものなら聴いてみたいと思うのは私だけではないだろう。ソニーさん、ぜひ小澤メモリアルエディションとして出してください。ストラヴィンスキー研究においても重要な資料だと思うのだが。
で、聴いてみるとこれが凄い。ダイナミックレンジの大きいこの曲で60年代の録音であることに不安があるかと思ったらそんなことは全然なく、下手なデジタル録音より断然優秀なクリアな録音。何より脂の乗り切ったシカゴ響の管楽器が存分に鳴り響いており痛快。どんな眠い朝でもこれを聞けば目が覚めるのではないかと思える激烈さとともに、見通しの良さがもたらす色彩感の豊かさとリズム感が素晴らしい。シカゴ響にとっても春の祭典の録音はこれが最初で、若い小澤とともに並々ならぬ気合の入りようが伺え、尋常ならぬテンションの高さとパワーが炸裂している。特に最も難曲とされる最終章「生贄の踊り」は4分ちょうどと速い方だと思うが破綻もなく豪快に進んでいき、圧巻と言わざるを得ない。これを振った小澤はやはり天才だった。
小澤が録音した翌年、小澤より10歳年上のブーレーズがクリーヴランド管弦楽団と1969年に録音した春の祭典について、音楽評論家の吉田秀和は「このレコードの以前に出ていたすべての盤は、この前には色褪せたものになってしまった」(『世界の指揮者』ちくま文庫, p. 237)と書いているが、小澤の盤を聴いたうえでそう書いているのかは相当に疑問だと思う。
レコーディング:July 1, 1968, Orchestra Hall, Chicago
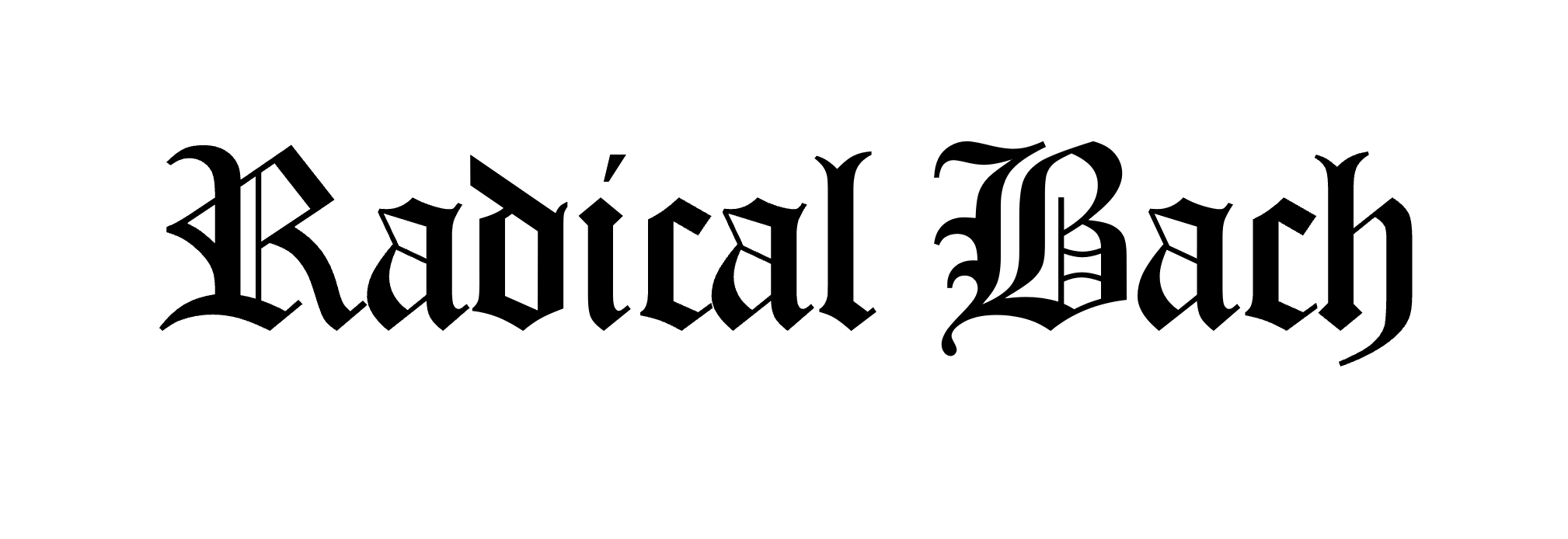



コメント