1960年代半ば、小澤征爾がピーター・ゼルキンをソリストに迎え、シカゴ響を振った1枚。当時小澤は30歳、ピーター・ゼルキンはまだ10代だった。ピーターとセイジは盟友とも言える間柄だったが、そのいきさつは村上春樹との対談『小澤征爾さんと音楽について話をする』にこうある。
ピーターは若い頃は、父親にものすごい反抗していたんです。けっこう問題があって。それで僕は頼まれたんですよ、親父さんに。ピーターのことをよろしく頼むって。だから彼が十八くらいのときから、ずっと親しく付き合ってます。僕はどうやらゼルキン先生には信用されていたみたいですね。セイジに頼んでおけば大丈夫だ、みたいに。それでピーターとは最初の頃、ずいぶん一緒にいろんなことをやりました。今でも仲はいいけど、その頃はトロントとかラヴィニアとか、そういうところに毎年行って、一緒に演奏してました。ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲ピアノにアレンジしたものなんかを、よくやりました
『小澤征爾さんと音楽について話をする』(新潮文庫、2014), pp. 99-100
対談の中で村上春樹は、60年代の小澤の演奏の中でも特に優れたものとしてこのバルトークと、トロントとのベルリオーズ『幻想』、そしてストラヴィンスキーの『春の祭典』を挙げている。
バルトークと言えばピアノを打楽器のように扱うのが特徴的だが、ピアノ協奏曲第1番の冒頭の不吉なピアノの連打、鮮烈なトランペット、これぞバルトークワールドである。
第一楽章は鮮烈な冒頭に続いて丁寧な管楽器とピアノの掛け合いが印象的だ。小澤征爾は村上春樹との対談の中で、「この時代はね、シカゴ・シンフォニーのブラスはもう世界で一番だった」(同、p.180)と語っているがそのハイレベルぶりが堪能できる。
第二楽章はアンダンテから。打楽器が常にベースを打ち続ける中、管楽器とピアノが掛け合う。アレグロでパーカッションが盛り上げ、そのまま間を置かず第三楽章へ。集中力の高い演奏が続く。
第3番は第1番とは打って変わって平和的な曲調でスタートする。ピアノも打楽器というよりはピアニスティックな響きになっている。って、このピアノを10代の若者が弾いているとは度肝を抜かれるばかりだ。
第二楽章はドラマの回想シーンで使われるんじゃないか思える内省的で美しい音楽だ。バルトークの音楽の中でも至上の美しさではなかろうか。ゼルキンの若いピアノがよく、そこに弦楽器が優しく伴奏するその様がたまらない。終わり近くのダイナミックな曲調の場面で唸っているのはゼルキンだろうか。
そして3楽章のリズム感と勇ましさはいかにもバルトークらしい。ピアノソロ部分がまた美しい。圧巻のフィナーレは必聴に値する。
レコーディング:July 11, 1966 (No. 1); June 28, 1965 (No. 3), Orchestra Hall, Chicago
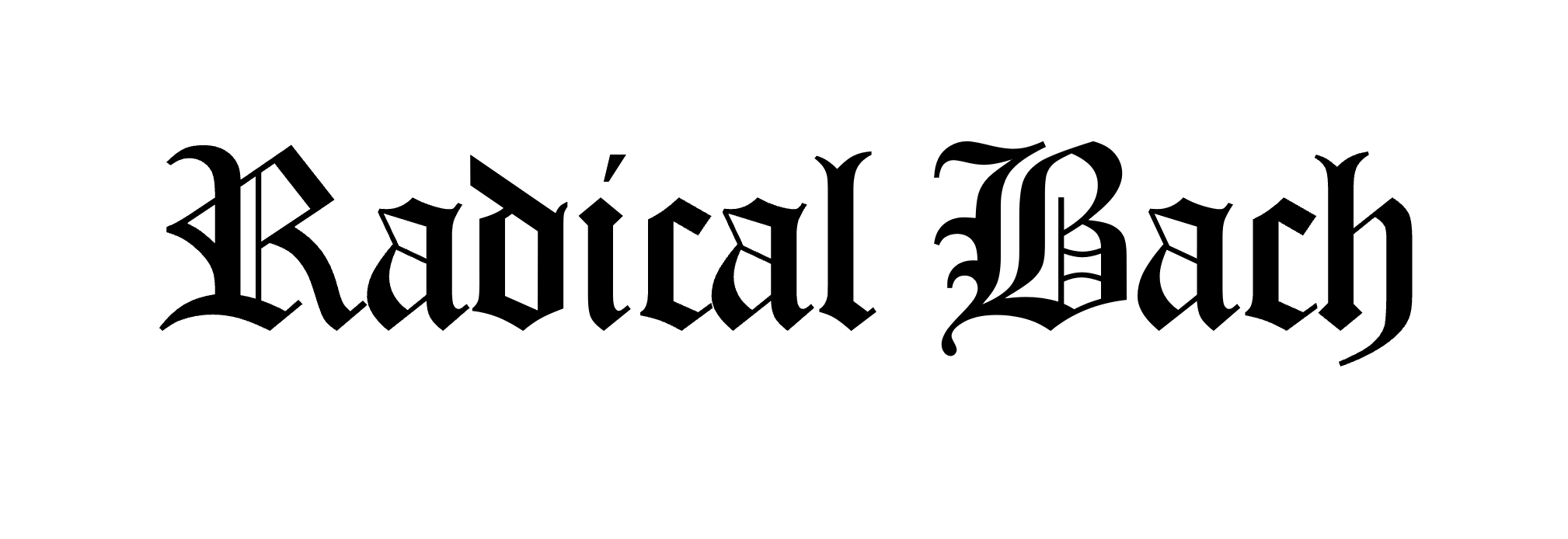



コメント