モーツァルトの交響曲第4番 ニ長調 K. 16は1765年、モーツァルトがわずか9歳にして作曲した交響曲。イタリア風の三楽章構成で、ファンファーレ音型の印象的な第一楽章、典雅なる第二楽章、そして華やかで舞曲風の第三楽章から成る。演奏時間は10分程度で聴きやすい。
モーツァルトは父レオポルトに連れられて7歳から10歳までの3年半に渡ってドイツの各地やパリ、ロンドンを旅している。旅行の目的は教育熱心な父親が息子に当時の最先端の流行を幅広く経験させようとしたことと、神童として名声を広めるべく各地の王侯貴族の下で演奏することだった。ロンドンには1764年4月から翌年6月まで滞在しており、交響曲第4番を含め、いくつかの交響曲が作曲されたという。
名盤聴き比べ
モーツァルトの交響曲を聴くにあたって最初の分かれ目はモダン楽器か、古楽器か、というところだろう。聴いてみると分かるが一般にモダン楽器による演奏は音が分厚く豊かな感じがするのに対して古楽器による演奏はシャープでより室内楽的な印象を受ける。ただ、モダンであっても古楽器のピリオド奏法を意識した演奏をしている場合もあり、明確に白黒つけられるわけではない。また、繰り返しの有無や、通奏低音にチェンバロが使われたり使われなかったりするのでその点でも印象が変わってくる。
以下、録音年代順に私の所持盤を聴いてみる。
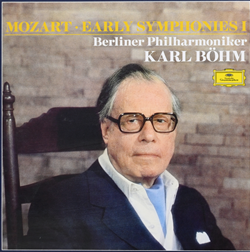
カール・ベームが1968年にベルリン・フィルを振った演奏。第一楽章からゆっくりで音そのものに浸れる演奏。第二楽章も雄大でいかにもベームらしい。第三楽章は前半のみ繰り返し。
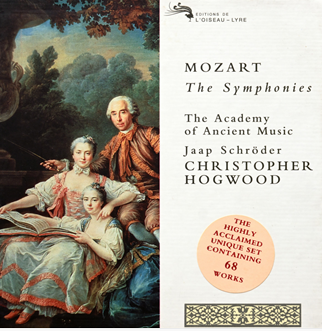
クリストファー・ホグウッドとエンシェント室内管弦楽団による1985年の演奏。出だしのホルンが子気味よい。第一楽章はキビキビとして威勢がいい。第二楽章のアンダンテもちょうどいい速さ。第三楽章も軽快で鋭い弦の響きがいかにもホグウッド盤。
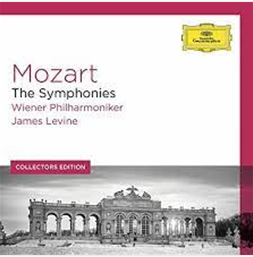
ジェームズ・レヴァインがウィーンフィルを振った1990年の演奏。これぞウィーンフィル!という美しい弦の響き。第一楽章はかなり軽快に飛ばしている。第二楽章はウィーンフィルのこの演奏が至上ではなかろうか。第三楽章は出だしが少し重い気もするが爽快にフィニッシュ。
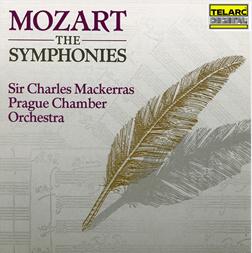
チャールズ・マッケラスが1990年にプラハ室内管弦楽団を指揮した演奏。第一楽章は繰り返しなし。室内管弦楽団にしてはちょっとオーケストラが厚すぎる気もする。第二楽章も繰り返しなし。第三楽章は前半のみ繰り返しあり。きれいにまとまってはいるのだがどこか古めかしい感じもする。
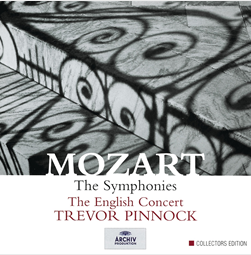
トレヴァー・ピノックがイングリッシュ・コンサートと1992年に録音した演奏。第一楽章は繰り返しなし。第二楽章と第三楽章は繰り返しあり。チェンバロが使われているがピノック自身がチェンバロ奏者であることを考えると弾き振りだろう。そのためか同じ古楽器でもホグウッドより若干丸くなっている気もするが、それはそれで全体のアンサンブルが整っており非の打ち所がない。
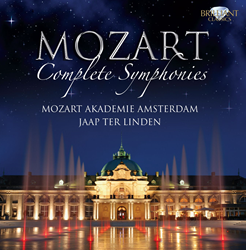
ヤープ・テル・リンデンとモーツァルト・アカデミー・アムステルダムによる2002年の演奏。こちらも古楽器による演奏。チェンバロは使用されていない。第一楽章は繰り返さず、第二、三楽章は繰り返す。丁寧な演奏で楽譜をたどりながら聴くには良いのだが、古楽器ならではの粗さというか、トンガリ感がなく平板な印象。
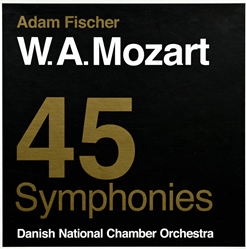
アダム・フィッシャーとデンマーク国立放送シンフォニエッタによる2012年の録音。スタッカートが強く劇的でテンポも揺らしてくる。この演奏は今までにない演奏であることは確かなのだが好みは分かれるだろう。第一楽章は繰り返さず、第二、三楽章は繰り返している。第三楽章でヴァイオリンの音階が2音で一気に上がるところがあるのだが、冗談で遊んでいるのか?と思えるような演奏で笑える。
まとめ
以上、表にまとめると下記の通り。なお、第一、ニ、三楽章の演奏時間をそれぞれ1st, 2nd, 3rdの欄に記載し、一番早い演奏を青マーカー、遅い演奏を赤マーカーで示している。繰り返しが省略されている場合は太字で示している。第一楽章についていえばホグウッドが一番速く、それとほぼ同じくらい早いのがレヴァインだった。第二楽章で意外なのはベームが最速の部類に入っていること。第三楽章のスピード感はピノックが一番だ。第一楽章を繰り返しているのはベームとレヴァインだが、新モーツァルト全集では繰り返しがないものとされていることもあり、その他の演奏は繰り返されていない。
| 録音年 | 指揮者 | オーケストラ | モダン/古楽器 | 演奏時間(計) | 1st | 2nd | 3rd | チェンバロ |
| 1968 | カール・ベーム | ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | モダン | 11:00 | 5:01 | 3:44 | 2:15 | なし |
| 1985 | クリストファー・ホグウッド | エンシェント室内管弦楽団 | 古楽器 | 8:58 | 2:10 | 3:43 | 3:05 | あり |
| 1990 | ジェームズ・レヴァイン | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | モダン | 11:39 | 4:21 | 4:05 | 3:13 | あり |
| 1990 | チャールズ・マッケラス | プラハ室内管弦楽団 | モダン | 7:20 | 2:15 | 3:02 | 2:05 | あり |
| 1992 | トレヴァー・ピノック | イングリッシュ・コンサート | 古楽器 | 9:05 | 2:14 | 4:04 | 2:47 | あり |
| 2002 | ヤープ・テル・リンデン | モーツァルト・アカデミー・アムステルダム | 古楽器 | 9:21 | 2:23 | 3:46 | 3:12 | なし |
| 2012 | アダム・フィッシャー | デンマーク国立放送シンフォニエッタ | モダン | 8:56 | 2:16 | 3:44 | 2:56 | なし |
こうしてみると全楽章をすべて繰り返し省略なしでやっているのはレヴァインのみで、対極に全楽章とも省略したのはマッケラスのみ。第一楽章は繰り返さない方が主流のようだがベームのように繰り返してのんびり音に浸るような演奏も悪くないと思う。個人的にはレヴァイン&ウィーンフィルはその響きが美しくて外せない演奏。古楽器の面白さで言えばピノックもよいがホグウッドが最上のように思う。マッケラスは残響が多く音が濁っていて今一つ。リンデンは平板でフィッシャーはエキセントリック、といったところだろうか。
なお、モーツァルトの交響曲全集についてはこちらの記事でまとめているのでよかったらどうぞ。
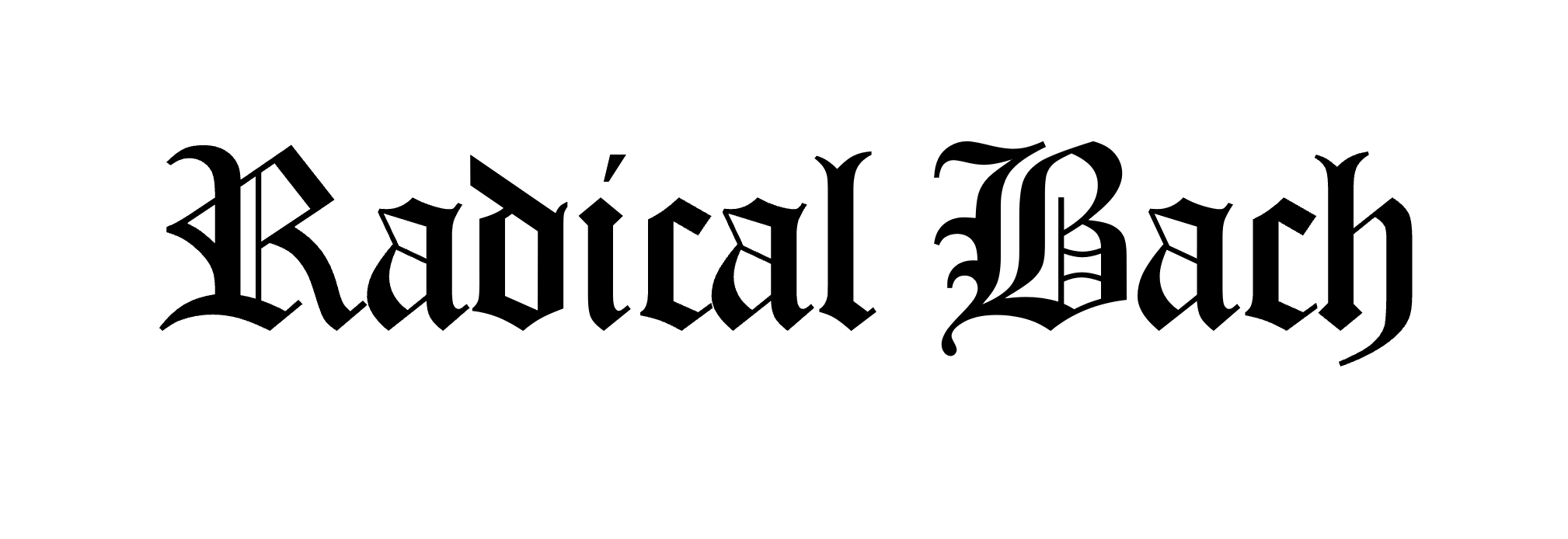

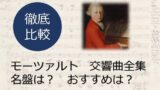

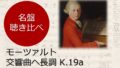
コメント