モーツァルトの交響曲第1番 変ホ長調 K. 16は1764年、モーツァルトがわずか8歳にして作曲した最初の交響曲。素直に美しく、快活で幸せな気分になる交響曲で、モーツァルトの交響曲の中でも個人的に印象深い傑作。第二楽章でホルンが奏でるモチーフは最後の交響曲『ジュピター』のフィナーレで用いられていることでも知られる。一周回って共通項があるというのはウロボロスの蛇を連想する意味深さがあり、面白い。
モーツァルトは父レオポルトに連れられて7歳から10歳までの3年半に渡ってドイツの各地やパリ、ロンドンを旅している。旅行の目的は教育熱心な父親が息子に当時の最先端の流行を幅広く経験させようとしたことと、神童として名声を広めるべく各地の王侯貴族の下で演奏することだった。ロンドンには1764年4月から翌年6月まで滞在しており、交響曲第1番を含め、5曲の交響曲が作曲されたという。
名盤聴き比べ
モーツァルトの交響曲を聴くにあたって最初の分かれ目はモダン楽器か、古楽器か、というところだろう。聴いてみると分かるが一般にモダン楽器による演奏は音が分厚く豊かな感じがするのに対して古楽器による演奏はシャープでより室内楽的な印象を受ける。ただ、モダンであっても古楽器のピリオド奏法を意識した演奏をしている場合もあり、明確に白黒つけられるわけではない。また、通奏低音にチェンバロが使われたり使われなかったりするのでその点でも印象が変わってくる。
以下、録音年代順に私の所持盤を聴いてみる。
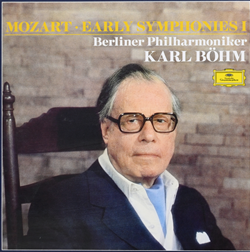
カール・ベームが1968年にベルリン・フィルを振った演奏。弦楽器が分厚いが何人で弾いているのだろうか。チェンバロは用いられていない。大編成のオーケストラを活かしたダイナミックに表情をつけた演奏でありながら不自然な感じはなく、第1番にして崇高なる名作の印象を深くするような秀演。
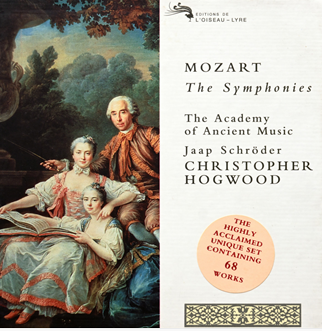
クリストファー・ホグウッドとエンシェント室内管弦楽団による1985年の演奏。チェンバロが伴奏する。エンシェント管はホグウッドが創設したイギリスのオリジナル楽器オーケストラ。味付けあっさり目のスピード感のある演奏で聴いていると非常に楽しい。個人的に第2楽章のテンポ感は後述のレヴァインやピノックよりはこれくらいの速さが好み。やや残響音が長め。
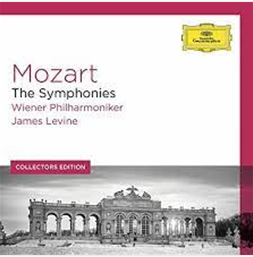
ジェームズ・レヴァインがウィーンフィルを振った1990年の演奏。チェンバロがアクセントになって快い。ウィーンフィル特有の弦楽器の美音とレベルの高いアンサンブルが天国的な世界を生み出している極上の演奏。第二楽章はゆっくり目で6分かかっている。
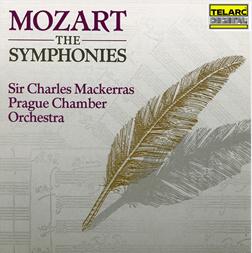
チャールズ・マッケラスが1990年にプラハ室内管弦楽団を指揮した演奏。室内管弦楽団というだけあってオーケストラは小規模編成。それでいて弦楽器は響きが豊かで美しくてホレボレする。チェンバロは鳴っているのだがあまりチェンバロ感のない音である上に音量がやけに小さく、別になくてもよかったんじゃないかと思う。モダン楽器を使いながらもピリオド奏法を意識しており、全体的に快速モード。
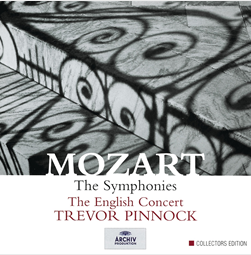
トレヴァー・ピノックがイングリッシュ・コンサートと1992年に録音した演奏。イングリッシュ・コンサートはピノックが創設したイギリスの古楽器オーケストラ。チェンバロが使われているがピノック自身がチェンバロ奏者であることを考えると弾き振りだろうか。第一楽章はやや速めでサッパリした印象。第二楽章はレヴァインよりもゆっくりで6分10秒ほど。第三楽章はうって変わって快速モードで2分の演奏になっている。
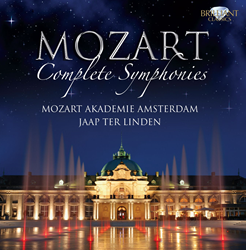
ヤープ・テル・リンデンとモーツァルト・アカデミー・アムステルダムによる2002年の演奏。こちらも古楽器による演奏。チェンバロは使用されていない。楽器間のバランスが悪くやや素人集団的に聴こえるのは気のせいだろうか。
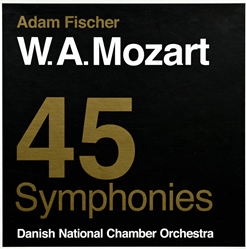
アダム・フィッシャーとデンマーク国立放送シンフォニエッタによる2012年の録音。出だしのダッダッが強く切られており他にない印象を受ける。アクセントの位置が他の演奏と明らかに違っておりかなり個性的。レガートをかけずにピリオド奏法を意識しているような印象だが、それが時々耳慣れない響きを生じさせることもある。オーケストラはモダン楽器ながら小規模編成で室内楽的な雰囲気を味わうには良い演奏。
まとめ
以上、表にまとめると下記の通り。なお、第一、ニ、三楽章の演奏時間をそれぞれ1st, 2nd, 3rdの欄に記載し、一番早い演奏を青マーカー、遅い演奏を赤マーカーで示している。1stと2ndは太字のベーム&ベルリンフィルが一番短くなっているが、これは速く演奏しているためではなく、繰り返しを省略しているためである。
| 録音年 | 指揮者 | オーケストラ | モダン/古楽器 | 演奏時間(計) | 1st | 2nd | 3rd | チェンバロ |
| 1968 | カール・ベーム | ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | モダン | 11:29 | 4:45 | 4:21 | 2:23 | なし |
| 1985 | クリストファー・ホグウッド | エンシェント室内管弦楽団 | 古楽器 | 13:01 | 5:41 | 5:21 | 1:59 | あり |
| 1990 | ジェームズ・レヴァイン | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | モダン | 14:17 | 6:03 | 6:03 | 2:11 | あり |
| 1990 | チャールズ・マッケラス | プラハ室内管弦楽団 | モダン | 12:31 | 5:54 | 5:01 | 1:36 | あり |
| 1992 | トレヴァー・ピノック | イングリッシュ・コンサート | 古楽器 | 14:01 | 5:49 | 6:13 | 2:01 | あり |
| 2002 | ヤープ・テル・リンデン | モーツァルト・アカデミー・アムステルダム | 古楽器 | 12:41 | 5:58 | 5:03 | 1:40 | なし |
| 2012 | アダム・フィッシャー | デンマーク国立放送シンフォニエッタ | モダン | 12:31 | 6:19 | 4:43 | 1:29 | なし |
こうしてみるとフィッシャーは第一楽章を最も遅く演奏しながら第二、第三楽章は最速という奇妙なことになっていることがよく分かる。アンサンブルの美しさ、音色の美しさの点ではレヴァイン&ウィーンフィルの演奏が最上だと思う。ただ、第二楽章の深みのようなものはベーム&ベルリンフィルが優れている。古楽器ではピノックかホグウッドなのだが個人的にはテンポの速いホグウッドの方が古楽器的スマートさが味わえて好み。モダン楽器を利用しつつ古楽器でされているような小規模編成で、ということであればマッケラスを推したい。
なお、モーツァルトの交響曲全集についてはこちらの記事でまとめている。
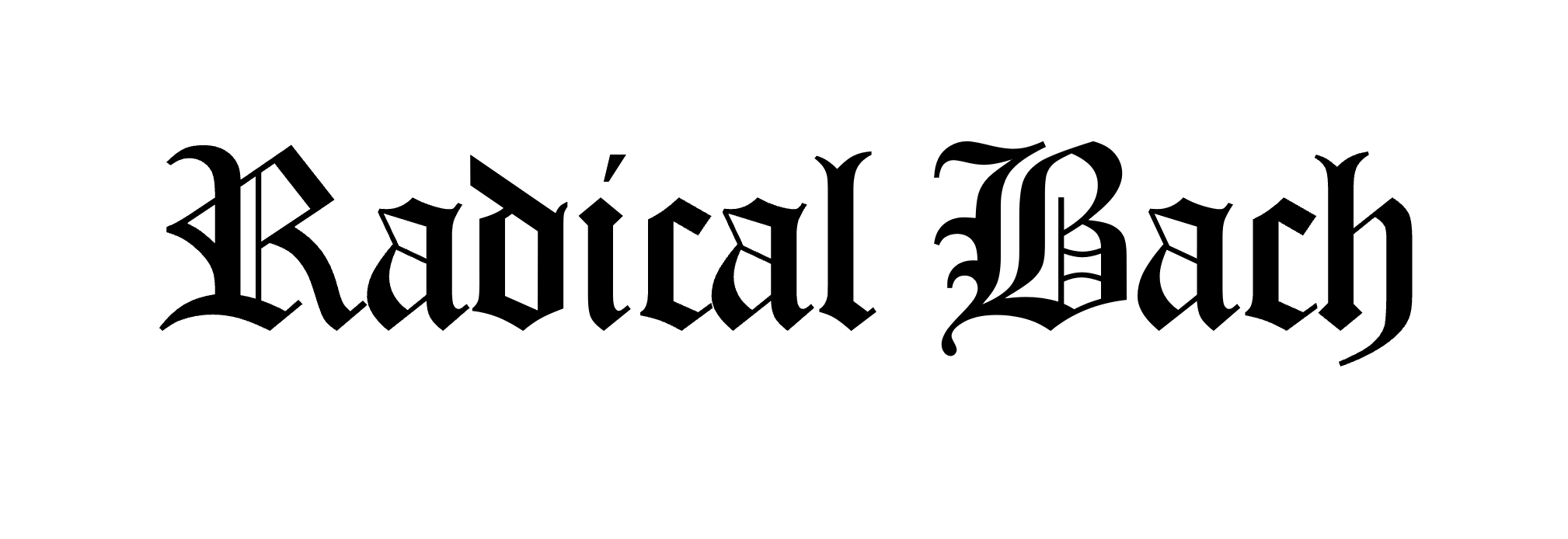

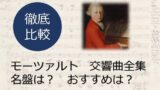
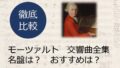

コメント