2024年2月9日金曜日、読売交響楽団の定期公演の場で、私は小澤征爾の訃報に接した。コンサートの前半、バルトークの「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」を聴き終え、休憩をはさんで武満徹のノヴェンバー・ステップスが始まろうかという時、指揮者の山田和樹がマイクを持って現れた。「もともとしゃべる予定ではなかったのですが、悲しいお知らせがあります・・・小澤征爾先生が亡くなられました。」会場からは「えっ」という声、山田自身も動揺を隠せない様子だった。そのあとの話の内容はだいたい次のようなものだった:発表のタイミングから考えて実際に亡くなられたのはもう少し前だろうが、奇しくも小澤征爾が成り立ちに深く関わり、初演を行ったノヴェンバー・ステップスを演奏するタイミングに重なったこと、当時日本人のソリストというだけでリハーサルから人がいなくなるなど差別的な状況のなかで演奏されたということ、ノヴェンバー・ステップスが初演された際のコンサートプログラムにはベートーヴェンの交響曲第2番が入っており、今日のプログラムもそのオマージュであること、そして黙祷することも考えたがコンサートを悲しいものにすることは小澤先生も望んでいないだろうから代わりにこの演奏を小澤先生に捧げたい、ということだった。
そのようなわけでノヴェンバー・ステップスは非常に意義深い演奏になった。強い吐気が生み出す尺八のむせび泣くような音、激しく撥が打ち付けられる緊迫した琵琶の音、それらはまるで小澤の死を嘆き悲しんでいるかのようだった。旋律、和音、律動の音楽の3要素から律動が解体され、まどろむような時空間を現出させる武満サウンドは生と死についての沈思を強制するような迫力があった。
ノヴェンバー・ステップスの成立過程については立花隆の『武満徹・音楽創造への旅』が詳しい。この曲を初演した小澤は当時32歳だったが、当時のことを次のように振り返っている。
「なにか責任感みたいのを感じていたんです。ぼくが日本人で、はじめてニューヨーク・フィルから日本人に作曲を依頼させ、しかもその曲の中に日本の古典楽器を入れさせた。それによって二人の日本人演奏者を引き込んだ。どちらも、ぼくが最終決定権者として決めたわけじゃないけど、ぼくが深く関与しているわけです。バーンスタインに『エクリプス』を聞かせたのもぼくなら、武満さんに、琵琶と尺八をオーケストラに合わせてみたいと相談されて、ぜひやってみろとすすめたのもぼくのわけです。武満、琵琶、尺八の取り合わせで、絶対素晴らしいものができると力説してきたわけですよ。これはもう絶対失敗するわけにいかないと思いましたね。ぼくは当時まだ若かったですからね。ニューヨークじゃまだチンピラ扱いされてるみたいなところもありましたから、つまらない曲だったら、なんだこんなものを推賞しやがってということになるでしょう」
立花隆. 武満徹・音楽創造への旅 (文春e-book) (p.823). 文藝春秋. Kindle 版.
「それとぼくが心配していたのは、ニューヨークのオーケストラの反応なんです。あの曲は、聞いてすぐ誰でも、これは素晴らしい曲だと思えるような曲じゃありませんからね。ニューヨークの連中がどういう反応を示すか、本当に心配だったんです。もしかして、すごく不謹慎なふるまいに及んで、武満さんに失礼なことをするんじゃないかと思ったんですよ。琵琶とか尺八とか、西洋音楽とは全く作法が違うでしょう。目をつぶってうなり声を出したり、琵琶のバチで胴をビシャッと叩いたりとか。ああいうのが、どう受け入れられるか心配だったんです」
演奏会で山田の話にもあったように、リハーサルでは琵琶と尺八を担当する鶴田と横山の二人が舞台に出てきただけで、ニューヨーク・フィルの団員たちが笑い転げて演奏にならなかったという。しかもリハーサルはたったの2回。作曲家・武満徹と指揮者・小澤征爾、そして日本の伝統楽器の命運を左右する緊張の初演を迎える。当日のことを小澤征爾はこう振り返っている。
「演奏が始まると、はじめ好奇心でなんとなくざわついていた会場が、音楽の真実さ、強さ、美しさに引っ張られて、みなシーンとしちまうのが感じられる。指揮としてはあまり活躍するところがない曲なのに、どうしてか、エネルギーをたくさん使わねばならん曲だわい、とも思う。(中略) ぼくが感激するのは当然として、西洋の客がどう受け取るかと思ってたら、大成功なのでまず安心した。オーケストラの連中もステージの上でブラボー、ブラボーをやっていた。 ぼくは、くたびれきったためかもしれないが、だんだん頭の中がひとりぼっちになって考え始めた。 この音楽は、ぼくの血の中で、肉の中で、心の中で、またぼくがこれまでに得た音楽教養の中で、いちばんしゃべりたかったことをしゃべっている、というようなことだ。 聴きに来ていた作曲家のペンデレツキ(ポーランド)やコープランド(アメリカ)は真赤な顔をして、感激、興奮していた。二日目に来たバーンスタインは『まあ、なんという強い音楽だ。人間の生命の音楽だ』と涙を流していた」
立花隆. 武満徹・音楽創造への旅 (文春e-book) (p.823). 文藝春秋. Kindle 版.
この曲は1967年11月9日の初演の後、11月28日にはトロント交響楽団を指揮してカナダ初演、同年12月8日に録音され翌年にレコードがリリースされている。各地で武満の作品を演奏し、その名を世界に知らしめるのに小澤が果たした役割は計り知れないほど大きい。その録音を再聴しつつ、小澤に感謝の意と追悼の意を表したい。
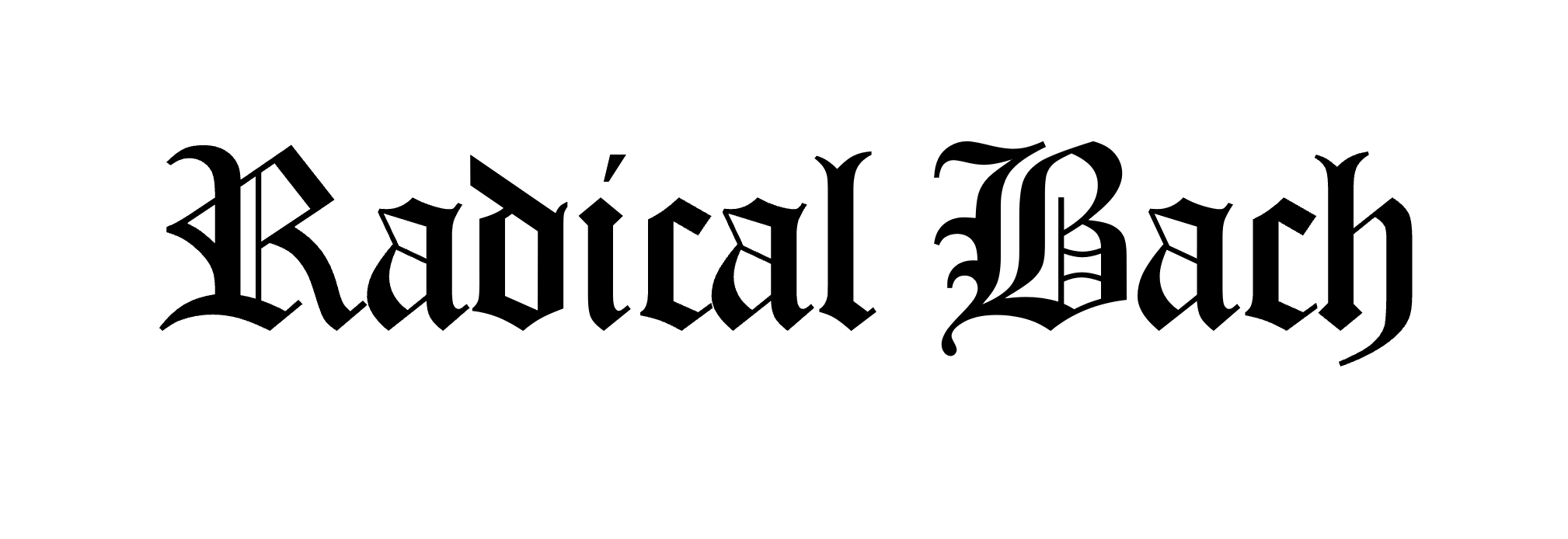


コメント